病気やケガで入院したあと、「急性期」「回復期」「維持期」という言葉を聞いたことはありませんか?
これは、病気の治療から在宅生活までの流れを3つのステージに分けて考える考え方です。
それぞれの時期には、医療機関やリハビリ、介護の役割が異なります。
この記事では、「急性期・回復期・維持期」の意味と特徴、そして各医療機関の役割をわかりやすく解説します。
これを読むことで、「今どの時期なのか」「次にどんな支援があるのか」がスッキリ理解できるはずです。
急性期・回復期・維持期とは?まず全体の流れを理解しよう
病気の発症から在宅生活までの「3つのステージ」
急性期・回復期・維持期とは、病気やケガの「経過」を3つの段階に分けたものです。
- 急性期:命を守るための治療を最優先する時期
- 回復期:身体機能を回復させ、日常生活へ戻る準備をする時期
- 維持期:安定した状態を保ちながら、再発や悪化を防ぐ時期
この3つをつなぐことで、「病気を治す医療」から「生活を支える医療」へとスムーズに移行できます。
なぜ分ける必要があるの?目的と背景
医療の進歩により、多くの患者が救命後もリハビリや在宅生活を続けられるようになりました。
そのため、病気の段階に応じて適切な医療・介護を提供することが重要になったのです。
医療・リハビリ・介護のつながりを知ることの大切さ
「どの病院に行けばいいの?」「退院後はどうなるの?」と不安を感じる人も多いでしょう。
各時期の特徴を知ることで、医療機関の選び方や今後の見通しを立てやすくなります。
急性期とは|命を守るための「治療中心の期間」
急性期病院で行われる主な治療とケア
急性期は、病気やケガが発生してからすぐの時期で、命を救うことが最優先です。
手術、集中治療、点滴や投薬など、症状を安定させるための医療行為が行われます。
入院期間の目安とリハビリの始まり
入院期間は短く、平均1〜2週間ほどです。
症状が落ち着き始めると、リハビリ専門職(理学療法士など)が早期から関わり、寝たきりを防ぐ取り組みを始めます。
医療スタッフの役割
- 医師:治療方針の決定と全身管理
- 看護師:24時間体制のケア
- リハビリ職:体力や機能を取り戻すためのサポート
回復期とは|「治療から生活復帰」へ向かうリハビリの期間
回復期リハビリ病院とは?
回復期は、身体機能を取り戻して自宅や社会に戻るためのリハビリを行う期間です。
「回復期リハビリテーション病棟」では、1日最大3時間の集中的リハビリが受けられます。
日常生活動作(ADL)を取り戻すリハビリ内容
歩行練習、着替えや食事の練習など、生活に直結した訓練が中心です。
目標は「できることを増やすこと」。家で安心して暮らせるよう支援します。
家族の関わり方と退院支援のポイント
退院に向けて、家族も一緒に介助方法や生活環境を整える練習を行います。
医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーが、退院後のサービス調整をサポートします。
維持期とは|在宅や介護施設で「今の状態を守る」期間
維持期の医療・介護サービスの例
病状が安定したら、自宅や施設での生活を続けながら、状態を維持する時期になります。
利用される主なサービスは、
- 訪問リハビリ
- 通所リハビリ(デイケア)
- 介護サービス(デイサービス、訪問介護)
などです。
地域包括ケアの中での維持期の位置づけ
維持期は、医療だけでなく地域全体で支える医療・介護の仕組み(地域包括ケア)の中心です。
医師・看護師・リハ職・介護職・家族が連携して生活を支えます。
「支える医療」から「支え合う地域」へ
病気を「治す」だけでなく、「支えながら生きる」時代へ。
維持期の支援は、患者本人のQOL(生活の質)を守る大切なステージです。
各医療機関の役割まとめ|急性期〜維持期のリレー構造
急性期病院 → 回復期病院 → 在宅支援の流れ
医療はチームリレーのように、患者の状態に合わせてバトンを渡していきます。
急性期病院が命を救い、回復期病院が生活機能を整え、在宅医療が支え続けます。
連携がうまくいくと患者・家族にどんなメリットがある?
- 回復がスムーズになる
- 再入院のリスクが減る
- 家族の負担が軽くなる
これが「地域包括ケアシステム」の理想的な姿です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 回復期と維持期の違いは何ですか?
A. 回復期は「できることを増やすリハビリの時期」、維持期は「今の状態を保つための時期」です。
回復期では積極的な訓練を行い、維持期ではリハビリや介護を通して生活の安定を図ります。
Q2. 回復期リハビリ病院にはどのくらい入院できますか?
A. 病気の種類によって異なりますが、おおむね60〜180日が目安です。
脳卒中や骨折後など、リハビリで生活機能の回復を目指す期間として設定されています。
Q3. 維持期になってもリハビリは続けられますか?
A. はい、続けられます。
維持期では、訪問リハビリやデイケア(通所リハ)などを利用し、在宅生活をサポートします。
医師の指示書があれば、医療保険や介護保険を使って継続可能です。
Q4. どのタイミングで在宅支援に切り替えるのがいいですか?
A. 医師やリハビリスタッフと相談し、日常生活動作が自立または安定したタイミングが目安です。
ただし、体力や家族の支援体制によって個別に判断されます。
Q5. 家族として何をしておけばよいですか?
A. 各時期での「情報共有」と「準備」が大切です。
急性期では治療内容を理解し、回復期では退院後の生活をイメージ、維持期では介護やサービス利用を整えておくと安心です。
まとめ|治療の先にある「生活を支える医療」を理解しよう
急性期・回復期・維持期は、それぞれに大切な役割があります。
病気が治るだけでなく、「その人らしく生きること」を支えるために医療と介護が連携しています。
家族としては、「どの時期にどんな支援があるか」を理解しておくことで、安心して次のステップに進めます。
医療はゴールではなく、「日常生活へ戻るための橋渡し」なのです。
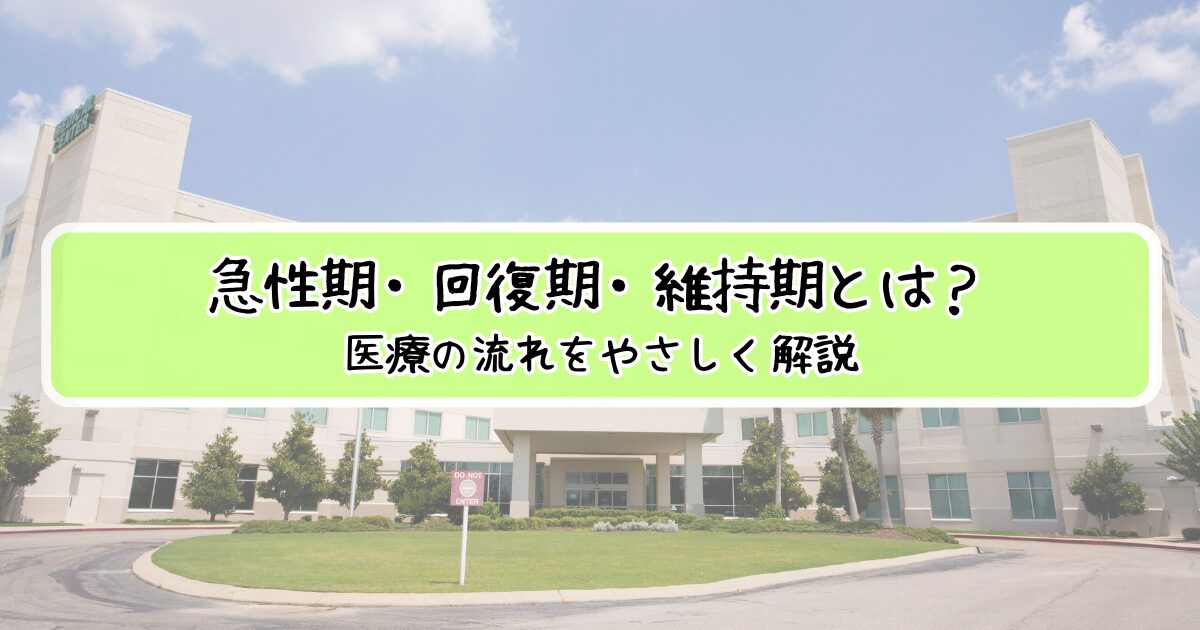


コメント