なぜ今「労働寿命」と「雇用寿命」が注目されているのか
私たちが生きる現代は、「人生100年時代」と呼ばれる長寿社会。
平均寿命が延びた今、60歳で定年、65歳で引退というこれまでの常識は通用しなくなっています。
しかし現実を見ると、「まだまだ働けるのに、働く場がない」「健康でも雇用契約が打ち切られる」といった声が増えています。
この“働けるのに働けない”というギャップの背景にあるのが、「労働寿命」と「雇用寿命」という2つの概念です。
どちらも「働く期間」を表す言葉ですが、意味は大きく異なります。
「労働寿命」は自分が働く能力を保てる期間、一方で「雇用寿命」は企業が雇い続けてくれる期間。
これからの社会では、自分の労働寿命のほうが長く、雇用寿命のほうが短くなる傾向が強まっています。
その差をどう埋めるかが、これからのキャリアの分かれ道となるのです。
労働寿命とは?— 働く力を持ち続ける期間
「労働寿命」とは、健康面・スキル面・意欲面を含めて“働ける力を持ち続けられる期間”のことです。
たとえば、70歳を超えても心身ともに健康で、人に価値を提供できるスキルを持っていれば、その人の労働寿命はまだ続いているといえます。
つまり労働寿命は、「働く体力・知力・気力を維持できる期間」であり、「何歳まで働けるか」を決めるのは企業ではなく“自分自身”です。
労働寿命を延ばす3つの要素
① 心身の健康維持
体が資本。どんなにスキルがあっても、健康を損なえば働くことはできません。
定期的な運動、バランスのとれた食事、質の高い睡眠を習慣化することが、労働寿命を延ばす第一歩です。
また、ストレス管理やメンタルヘルスケアも欠かせません。
② スキルアップ・リスキリング
社会は常に変化しています。
AI・デジタル化・グローバル化により、10年前のスキルが通用しない時代です。
そのため、「学び直し(リスキリング)」を通じて新しいスキルを身につけ続けることが重要です。
オンライン講座や通信教育、資格取得など、年齢に関係なく学び直す姿勢が求められます。
③ モチベーションと社会参加
「自分はまだ誰かの役に立てる」「社会とつながっていたい」という気持ちが、働く原動力になります。
ボランティア活動や地域との関わり、副業など、社会との接点を持ち続けることで、心の張り合いが生まれます。
雇用寿命とは?— 企業に雇われ続けられる期間
対して「雇用寿命」とは、企業に雇用され続けられる期間のことを指します。
つまり、「雇用契約を維持できる期間」「会社があなたを雇うと判断する期間」です。
日本の多くの企業では依然として「60歳定年」「再雇用で65歳まで」が一般的です。
しかし近年は、ジョブ型雇用や成果主義の広がり、AI・自動化の影響などにより、雇用寿命が短くなる傾向にあります。
雇用寿命が短くなる3つの理由
① AI・自動化の影響
AIやロボットの発展により、単純作業や定型業務は急速に機械に置き換えられています。
今後も「人でなければできない仕事」にシフトする動きは強まり、柔軟に対応できない人材は職を失うリスクが高まります。
② ジョブ型雇用の普及
従来の「年功序列」ではなく、「成果」と「専門性」を重視するジョブ型雇用が拡大中。
一つの企業で長く勤めるよりも、「即戦力」として採用されるケースが増えています。
つまり、同じ会社に居続けること自体が難しくなっているのです。
③ 企業の人件費削減と世代交代
少子高齢化による人件費の上昇を抑えるため、企業はシニア層の雇用を抑制する傾向にあります。
また、若手登用を進める企業も多く、「経験」よりも「新しい発想」が重視されるようになっています。
「労働寿命」と「雇用寿命」の違いを比較
| 項目 | 労働寿命 | 雇用寿命 |
|---|---|---|
| 定義 | 働く力を維持できる期間 | 企業に雇われ続けられる期間 |
| 主体 | 個人 | 企業 |
| 影響要因 | 健康・スキル・意欲 | 経営方針・制度・評価 |
| 延ばす方法 | リスキリング・健康管理 | 社内評価・再雇用制度 |
| 現状 | 延びつつある | 短縮傾向 |
| 対策 | 自立型キャリアの構築 | 社内外でスキルを磨く |
この表からも明らかなように、労働寿命と雇用寿命は一致しません。
むしろ今は「働ける期間(労働寿命)は延びているのに、雇われる期間(雇用寿命)は短くなっている」のが現実です。
労働寿命>雇用寿命の時代にどう生きるか
これからの時代、誰もが「雇用に頼らず働く力」を求められます。
そのためには、会社という枠を超えて、自分自身の市場価値を高める戦略が欠かせません。
キャリア戦略の3ステップ
① リスキリング(学び直し)で市場価値を高める
社会や技術の変化に適応するためには、学び続けることが不可欠です。
特に注目されているのが、デジタルスキル(AI、データ分析、マーケティング)や、コミュニケーション力、問題解決力。
年齢に関係なく学び直す姿勢が、労働寿命を延ばす最大の武器になります。
② パラレルキャリアや副業で働き方を多様化する
1つの企業だけに依存するのではなく、複数の活動を並行して行う「パラレルキャリア」や「副業」が注目されています。
自分の経験や専門性を活かして個人で仕事をすることで、雇用寿命に左右されない働き方が可能になります。
③ ウェルビーイング(幸福感)を意識した生き方
長く働くためには、心身の健康と充実感のバランスが欠かせません。
仕事のやりがい・人とのつながり・社会貢献といった“働く目的”を再定義することで、労働寿命をより豊かに延ばせます。
まとめ|自分の労働寿命を主体的にデザインしよう
今後の時代を生き抜くためには、「雇用される」ことよりも「自分で働ける力」を持つことが重要です。
✅ 健康を維持する
✅ 学び続ける
✅ 自分の強みを活かして働く
これらを意識的に続けることで、人生100年時代における「労働寿命」を長く、豊かに保つことができます。
まずは小さな一歩から。
- 興味のある分野のオンライン講座を受講する
- 地域活動や副業を通じて新しいつながりを作る
- 自分のキャリアを見直す時間を取る
その一歩が、未来の働き方を大きく変えるきっかけになります。
Q&A|よくある質問
Q1. 労働寿命は何歳くらいまで?
A. 健康と意欲があれば、70代、80代でも現役で活躍できます。
実際、シニア起業家やフリーランス講師、地域リーダーなど、「定年後も働く人」は増加しています。
Q2. 雇用寿命を延ばすにはどうすればいい?
A. 一つの企業に依存せず、「どの会社でも通用するスキル」を身につけることです。
資格、語学、マネジメント、デジタル知識などは年齢を問わず価値があります。
Q3. 定年後にできる仕事は?
A. 経験を活かしたコンサルティング、コーチング、オンライン教育、地域活動など。
近年はシニア向けフリーランスやNPO活動など、働き方の選択肢が大きく広がっています。
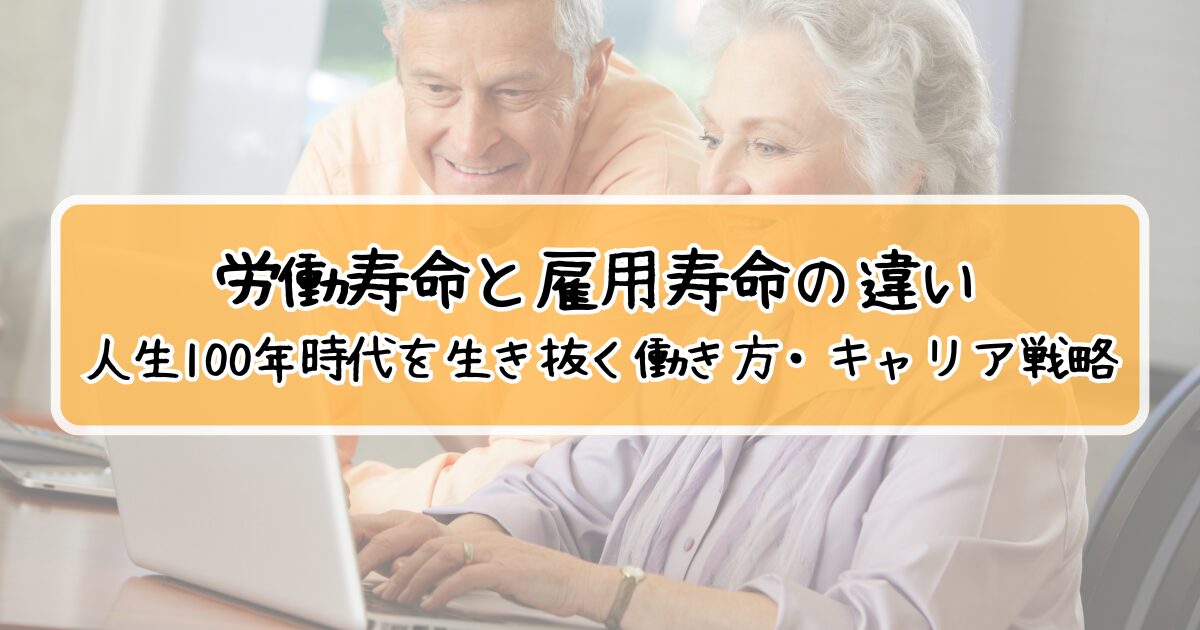
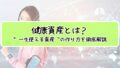
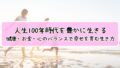
コメント