はじめに|なぜ「急性期・回復期・維持期」の理解が重要なのか
リハビリテーションの現場では、患者さんの「回復段階」に応じて関わり方が大きく変わります。
しかし意外と、「急性期」「回復期」「維持期」という言葉の意味を正確に説明できる人は多くありません。
これら3つの時期は、単なる病期の分類ではなく、医療・介護・在宅支援をつなぐリハ職の道しるべです。
自分がどの段階の支援を担っているのか、どんな目的を果たすべきなのかを理解することが、リハビリ専門職としての成長に直結します。
3つの時期の概要を整理しよう
リハビリの流れは、「急性期 → 回復期 → 維持期(生活期)」という3つのステップで構成されます。
それぞれの目的と特徴を整理してみましょう。
急性期(acute phase)
目的:生命維持と合併症・廃用の予防
この時期は、病気や手術直後など、全身状態が不安定な段階。
主なリハは、早期離床・呼吸訓練・関節可動域訓練など、命を守りながら体を動かす準備を整えることです。
理学療法士や作業療法士は、バイタルサインを確認しながら慎重に介入し、「寝たきり」になるリスクを防ぐ役割を担います。
「安静にすることが治療」だった時代から、「動かすことが回復を促す」時代へ——急性期リハはその象徴です。
回復期(recovery phase)
目的:身体機能と生活動作(ADL)の回復、家庭・社会復帰の準備
病状が安定し、集中的なリハビリが可能になった段階です。
回復期リハビリテーション病棟では、1日2〜3時間のリハビリを行い、歩行・食事・排泄・入浴など、生活動作の再獲得を目指します。
リハ職は患者や家族とゴールを共有しながら、「生活を取り戻すリハビリ」を進めます。
身体機能の改善だけでなく、心理的サポート・退院後の環境調整まで視野に入れるのがポイントです。
維持期(maintenance phase)
目的:生活の質(QOL)の維持と再発予防、社会参加の支援
自宅や施設での生活が始まると、リハビリは「治す」段階から「支える」段階へ移ります。
訪問リハビリや通所リハビリでは、運動習慣の定着や生活動作の維持を中心にサポート。
「再発させない」「自立を続ける」ことがこの時期のテーマです。
介護職・看護師・ケアマネージャーなどと連携し、生活全体を見守る視点が求められます。
各期で変わる医療機関の役割
急性期病院|命を守り、早期離床を進める
救急医療・手術直後などの医療介入を担う急性期病院では、医師主導のチーム医療の中でリハ職が重要な役割を果たします。
特に理学療法士は、患者の状態を的確に判断しながら「どのタイミングで動かすか」を見極め、回復期へのスムーズな橋渡しを行います。
回復期リハビリ病棟|生活機能を再構築する
回復期では、リハ職がチームの中心となり、多職種と協働して「生活の再建」を支えます。
歩行練習だけでなく、家屋評価や退院指導、家族教育も重要な業務です。
回復期の目標設定が曖昧だと、維持期での生活の質に影響が出るため、チーム全体でゴールを共有する力が問われます。
維持期(在宅・施設)|生活を支える地域のリハビリ
維持期では、リハ職が医療と介護の“つなぎ役”として機能します。
在宅生活の中で「自分で動ける時間をどう増やすか」「介助をどう減らすか」を考え、
本人・家族・地域を巻き込んだ支援を行います。
また、閉じこもり予防や社会参加支援など、“生きがいづくり”の支援も欠かせません。
リハ職の視点で見る「各期の関わり方と課題」
急性期:動かす勇気とリスク管理
全身状態が不安定な中で介入するため、安全性と判断力が何より重要。
「離床のタイミングを逃さない」「医療者間の認識をすり合わせる」など、
チーム連携が成否を分けます。
命に関わる緊張感の中で、リハ職が治療の一部として機能する責任感が求められます。
回復期:生活を再構築する支援
患者の希望と現実のギャップをどう埋めるかがポイントです。
ADL・IADLの訓練を通じて、「何ができるか」よりも「どう生きたいか」を共有し、
生活全体の再構築をチームで支えることが回復期リハの本質です。
維持期:継続支援と再発予防
「昨日できたことを今日もできる」ことを目指すのが維持期のリハビリ。
本人主体の生活を尊重しながら、習慣化・モチベーション維持を支援します。
訪問リハでは短時間でのアセスメント力や、介護職への助言スキルも重要です。
リハ職が意識すべき「地域連携と情報共有」
急性期から維持期への流れを途切れさせないために、医療機関同士・職種間の情報共有が欠かせません。
退院前カンファレンスでは、単に「歩ける・食べられる」だけでなく、
- 家庭環境や介護力
- 本人・家族の目標
- 社会資源の活用状況
といった情報を共有することで、次のステップの支援がスムーズになります。
維持期のリハ職から急性期・回復期へフィードバックを返す仕組みも、地域包括ケアの質を高めるカギです。
「支援は終わりではなく循環する」——その意識を持つことが、今後の医療・介護現場に求められています。
まとめ|3期を通して見える“リハ職の本質”とは
リハビリの目的は、「機能を取り戻すこと」ではなく「生活を取り戻すこと」です。
急性期では命と機能を守り、回復期では生活を再構築し、維持期ではその生活を続ける支援を行う。
この流れを理解し、各期での自分の役割を意識できるリハ職こそ、
真に「患者の人生に寄り添う専門職」といえるでしょう。
どのフェーズでも意識すべきは、「次の段階につなげる視点」。
それが、リハ職としての専門性を深め、地域社会に貢献するための第一歩です。
よくある質問(Q&A)
Q1.急性期・回復期・維持期の違いを簡単に説明すると?
A.
- 急性期:命を守るための治療と廃用予防の時期
- 回復期:失った機能を取り戻すためのリハビリ集中的時期
- 維持期:回復した生活を長く続けるための支援期
という流れで考えるとわかりやすいです。
Q2.どの時期のリハビリが一番大事ですか?
A.
すべての時期が重要です。
急性期で早期離床を進めることで回復期がスムーズになり、
回復期の生活訓練が維持期の自立を支えます。
3期は「リレー」のように連続していると考えましょう。
Q3.リハ職として各期で意識すべきポイントは?
A.
- 急性期:リスク管理と早期介入
- 回復期:生活目標の共有とチーム連携
- 維持期:再発予防と地域連携
どの段階でも「次の支援者につなぐ視点」を持つことが重要です。
Q4.維持期のリハビリで特に求められるスキルは?
A.
**「生活を見る力」と「伝える力」**です。
在宅では介護職・家族との協働が多く、運動指導よりも「支援体制のコーディネート」が大切になります。
おわりに
リハ職の仕事は、目の前の訓練だけでなく、その先の「生活」を見据えること。
急性期・回復期・維持期という流れを理解することは、
患者の人生を支えるリハ職としての土台になります。
どの現場にいても、“その先につながるリハビリ”を意識していきましょう。
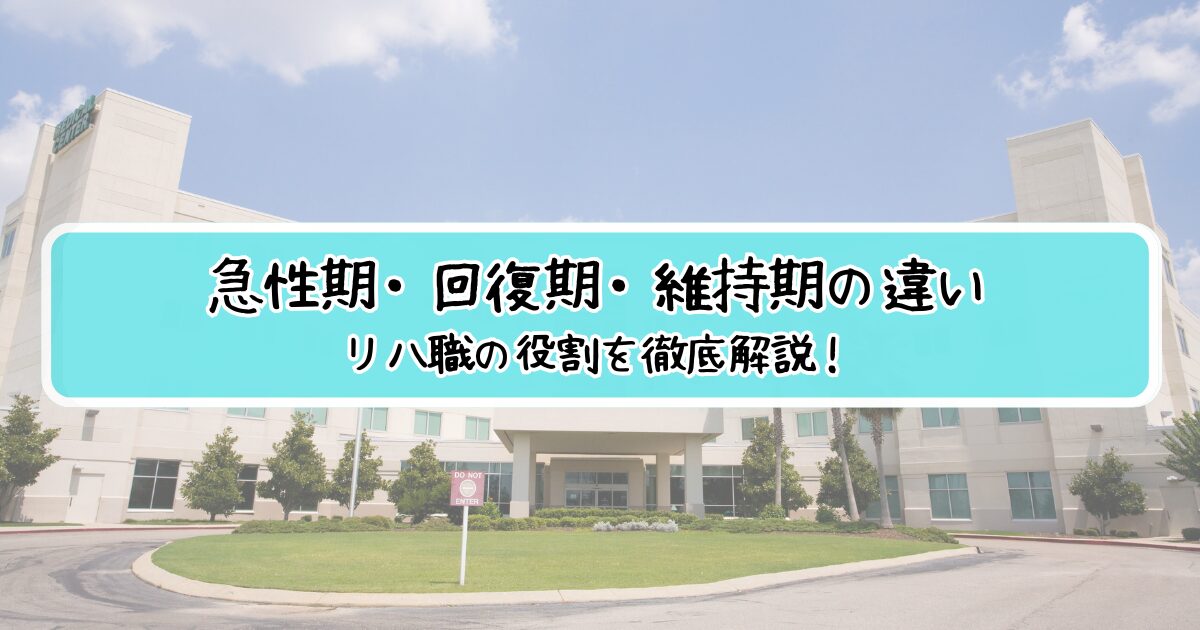


コメント